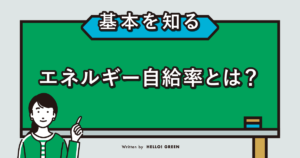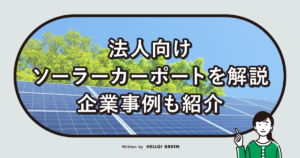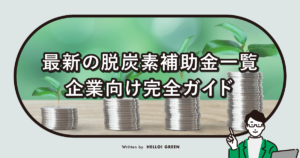【法人】太陽光発電導入のメリットは?中小企業向け補助金から節税対策まで総まとめ

電気やガソリンの価格が上昇する中、エネルギーの自給や売電目的で太陽光発電を導入する企業が見られます。今回の記事は「自社で産業用太陽光発電の導入を検討している」「太陽光発電の事業を法人化したい」という方に向けて、法人として太陽光発電に取り組むメリット・デメリットを解説しています。
導入時に注意したいポイントや節税対策についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
HELLO!GREENでは脱炭素経営の進め方に悩む中小企業さまに向けたお役立ち資料をご用意しています。ぜひご活用ください。
→資料を無料ダウンロードする
- 法人として太陽光発電を導入する主なメリットは、自家発電によるBCP対策、電気代の削減、企業価値の向上です。
- 法人として太陽光発電に取り組むデメリットは、税務や各種手続きを行う負担が増えることです。
- 太陽光発電設備を導入すると、法人への税額控除が適用できるケースもあります。
太陽光発電を含めた再エネ導入を国が後押し
近年、太陽光発電は急速に普及しています。2011年度から2022年度にかけて、発電量全体に占める太陽光発電の割合は23倍と、大幅に増加しました。
普及の背景には、国による「FIT制度」「FIP制度」が関係しています。これらの制度は、太陽光発電を導入する際にかかる設備投資に対して、「一定期間、定額・全量買い取り(FIT制度)」、または「補助としてプレミアムを交付(FIP制度)」といった形で支援するものです。

環境省『エネルギー転換部門におけるエネルギー起源CO2』を加工して作成
なぜ、国がこのように太陽光発電の導入をサポートするのでしょうか。理由は、発電によるCO2排出量を減らしたいからです。従来の化石燃料を使用した発電方法は、地球温暖化の一因といわれるCO2を排出するため、環境に配慮した別の発電方法を普及させたい狙いがあります。また、日本のエネルギー自給率の向上という目的もあります。
世界的な再生可能エネルギー(再エネ)の発電コストの低減化を追い風に、日本政府は今後も太陽光発電を含めた再エネの導入を促進していく見込みです。太陽光発電の導入を検討する際は、このような政府の動きもチェックしながら計画を立てましょう。
参考:経済産業省『再生可能エネルギーの導入状況』
【法人】太陽光発電を導入するメリット
太陽光パネルを設置することで、自社で発電した電気も使えるようになり、停電時の不安や電気料金の値上がりによる負担を軽減できます。太陽光発電の導入メリットについて、詳しく見ていきましょう。
メリット1.自家発電によるBCP対策
太陽光発電を導入するメリットとして、使用エネルギーの一部を自給できるようになることが挙げられます。蓄電池も活用すれば、さらに自給率を向上できるでしょう。
また、一定条件の下では停電中でも電気が使え、災害時への対策としても有効でしょう。このように、緊急事態による事業への損害をできるだけ減らすBCP対策は、経営基盤の弱い中小企業こそ重要です。
メリット2.電気代の削減
電気代の高騰に、頭を悩ませている企業の方も多いのではないでしょうか。太陽光パネルを設置して自家発電すれば、電気代を削減できるだけでなく、電気代高騰による自社への影響を最小限に抑えられます。以下は、一般的な電気料金における1kWh当たりの平均価格の推移を示したものです。

2011年の東日本大震災以降、電気料金は上昇傾向です。2022年度の産業向け電力における平均単価は、2010年度の2倍近くにもなっています。将来的に考えると、太陽光発電を導入し、一定のコストで電力を調達できるのは、企業にとってメリットが大きいのではないでしょうか。
参考:経済産業省『電気料金の変化』
メリット3.CO2排出削減によるビジネスチャンスの拡大
太陽光発電を含めた再エネ電力なら、電気利用に関するCO2排出量をゼロにできます。このような環境問題への取り組みは企業価値を向上させ、取引先の新規獲得や受注増加につながることも期待できます。
また、資金調達におけるメリットも。金融機関では、SDGs(持続可能な開発目標)に取り組む企業に対してさまざまな優遇制度を実施しています。金利の引き下げ、融資期間の延長などがあるので、金融機関のホームページなどで調べてみてはいかがでしょうか。
【法人】太陽光発電のデメリット
太陽光発電には、発電効率が日射量に左右されるというデメリットがあります。コストもかかるため導入時は慎重に検討することが重要でしょう。ここでは、太陽光発電のデメリットについて詳しく解説します。
デメリット1.税務や各種手続きの負担
10kW以上の太陽光発電設備を導入する場合は、「電気事業法」の規則に沿って関係各所に届け出を行う必要があります。また、法人として太陽光発電に取り組む際、減価償却費や固定資産税の計算も必要となり、複雑な会計処理を行うことも負担となるでしょう。補助金制度を活用する場合は、さらに書類作成や手続きの負担が増えます。
デメリット2.雨天や夜間は発電効率が低下
法人に限ったことではありませんが、太陽光発電は、くもり、雨など日射量が減少すると、発電量が少なくなります。「午後になると他の建物の影になる」など、立地や周囲の環境も発電量に影響するでしょう。営業時間が夕方~夜間といった会社では、日中に発電した分を売電したり、蓄電池を活用したりといった対策も検討が必要です。
ほかに、季節による変動もあります。冬場は日照時間が短くなるため、その分発電量も減少傾向に。夏季は日照時間は長いですが、気温上昇によって太陽光パネルの表面温度が上がることで、発電効率が低下します。夏季だからといって、日照時間が増えた分がそのまま発電量に反映されるわけではないことを、覚えておきましょう。
デメリット3.設備の導入と維持にかかるコスト
太陽光発電は、設備導入に大きなコストがかかります。近年の傾向として、工事費は下がっているものの、円安やインフレによる資材費が高騰している関係で、設置費全体としては低減傾向は見られません。地上設置(高圧)の平均の初期費用(直流ベース)は、15.2万円/kW(2023年10月時点)です。
そのほかのコストとして、太陽光発電を維持するには次のような費用もかかります。
太陽光発電の維持にかかる費用
・メンテナンス費用
・清掃費用
・機器の交換費用
・保険料
・税金
保険には、「災害による損害をカバーしたい」「災害時に太陽光パネルが落下して他者に損害を与えてしまった場合に備えたい」など、さまざまなケースを想定したものがあります。メーカーの保証内容も確認してから、加入を検討しましょう。
参考:経済産業省『太陽光発電の現状と自立化・主力化に向けたチャレンジ』
太陽光発電の導入を検討する際のポイント
法人として太陽光発電の導入を検討する際、考えておきたいポイントを紹介します。
| 導入の目的は? | 自家消費型、全量売電型、余剰売電型など |
| 設置場所は? | 屋根、敷地内、敷地外など |
| 契約方式は? | 購入、リース、PPAなど |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
導入の目的
「自家消費型太陽光発電」「全量売電型太陽光発電」など、目的によって、太陽光発電システムや配線のつなぎ方は異なります。太陽光発電で得た電力をどのように利用するのか、導入の目的を明確にしておくことが重要でしょう。
太陽光発電導入の目的は主に次の3つに分類できます。
| 自家消費 | 電気を自給することで電気代を削減したい |
| 全量売電 | 電気を売って収益を得たい |
| 余剰売電 | 自家消費を前提とし、余った電気を売りたい |
設置場所
太陽光発電の設置場所は、発電効率を高めるためにも重要です。日当たりがよいことを前提とし、十分なスペースがあれば敷地内に設置するのがよいでしょう。敷地面積が確保できなければ、自社建物の屋根やカーポートに設置するパターンもあります。どちらも難しい場合は、敷地外に設置を検討します。
契約方式
太陽光発電の導入にはさまざまな契約方式がありますが、屋根への設置では主に3つの方式があります。それぞれ特徴があるため、自社に合った方式を検討しましょう。
| 契約方式 | 特徴 |
|---|---|
| 購入 | 初期費用を支払い、自社の建物に太陽光発電システムを設置。導入後も、自社で維持管理を行う |
| リース | リース事業者に、自社の建物の屋根に太陽光発電設備を設置してもらい、発電した電力を自社で使用する。リース料を支払う |
| PPA (Power Purchase Agreement) | 自社の建物の屋根などを使って、発電事業者が太陽光発電設備を設置する。発電量に見合った対価を発電事業者に支払い、自社で電力を使用する |
リースまたはPPAの契約方式は、初期費用を抑えられるメリットがある一方、リース事業者や発電事業者と長期にわたる契約を締結します。契約内容によっては、太陽光発電を設置した自社の建物を移転できなくなるなど、デメリットもあります。コストだけでなく、さまざまな面から総合的に判断しましょう。
参考:環境省『はじめての再エネ活用ガイド(企業向け)』
太陽光発電を行う法人への税金。節税対策は?
法人が太陽光発電を導入した場合、自家消費・売電目的に関わらず「償却資産」として課税の対象となります。「固定資産税(償却資産)」のほか、「法人税」に影響が出るケースもあります。太陽光発電に関わる税金についてチェックしていきましょう。
太陽光発電に関わる税金
太陽光発電に関わる主な税金を、以下にまとめました。該当するかどうかは、契約方式のほか、発電の目的、主な事業との関係性によって異なります。
■国税
| 法人税 | 売電による収入があった場合 |
■地方税
| 法人事業税 | 売電による収入があった場合(電気供給業に該当するケース) |
| 固定資産税 | 太陽光発電設備を所有する場合 |
「法人税」とは、事業所得に応じて企業が支払う税金です。太陽光発電を導入し、全量売電または余剰売電による収入があった場合、他の収入と合わせて所得を計算し、金額に応じた法人税を国に納めます。
「法人事業税」は、法人が都道府県に納める税金です。太陽光発電で作った電気を売る「電気供給業」を主な事業とする場合や、ほかの事業も併せて行う場合など、事業の形態によって税額の計算方法は異なります。
「固定資産税」とは、土地、家屋、償却資産にかかる税金です。このうち太陽光発電は、償却資産に該当し、固定資産税を市町村に納めます。太陽光発電のために土地を購入した場合は、土地に対する固定資産税も別途かかります。
参考:総務省『法人事業税』『固定資産税』
中小企業ができる節税対策
太陽光発電の導入により、法人への税額控除が適用できるケースもあります。
| カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 | 設備投資などに対し、最大10%の税額控除(中小企業などは最大14%)、または50%の特別償却 |
| 中小企業経営強化税制 | 設備投資などに対し、取得価額の10%の税額控除、または即時償却 |
| 中小企業投資促進税制 | 設備投資などに対し、かかった費用の30%の特別償却、または7%の税額控除 |
※内容は2024年度に実施されたもの
税額控除(税金が減ること)のほかに、「特別償却」や「即時償却」という優遇措置もあります。これは、通常の減価償却の考え方とは異なり、対象の年度に設備投資額を通常より前倒しで計上できるものです。費用を多めに計上できることによって、所得が減るため、節税につながります。減価償却の総額は変わりませんが、資金回収を早めるメリットがあります。
事前に導入計画の認定を担当省庁などから受けることや、対象業種が定められているものもあるため、条件を確認しておきましょう。
参考:経済産業省『カーボンニュートラルに向けた投資促進税制』
参考:中小企業庁『中小企業経営強化税制』『中小企業投資促進税制』
太陽光発電の導入時に使える補助金
太陽光発電の導入費用の負担を軽減する手段として、補助金制度の活用もおすすめです。国のほか自治体で独自の補助金事業を設けているケースがあるため、チェックしてみてはいかがでしょうか。
例えば、東京都では2024年度に「地産地消型再エネ増強プロジェクト」を実施。事業所の屋根などに太陽光発電を設置した場合、中小企業への補助率は設置費用の3分の2(上限1億円)です。
太陽光発電に関する補助金制度については、以下の記事でも紹介しています。また、補助金事業以外に、導入に関するコンサルティングや低金利による融資など導入支援事業を行っている自治体もあります。
参考:東京都『太陽光発電設備の設置に対する東京都の助成事業』
【Q&A】太陽光発電に関するよくある質問
太陽光発電に関する質問にお答えします。
太陽光発電による売電収入の勘定科目は?
法人の場合で、自家消費を主とし、余剰売電で得た収入を計上する場合は、一般的に「雑収入」として計上します。一方、発電業者など売電事業を主とする場合は、「売上高」として処理します。
太陽光発電を行うのに、個人事業主か法人かで違いはある?
主な違いの一つとして、税金の種類の違いに伴い、所得に対する税率の範囲が変わることが挙げられます。
個人事業主の場合、法人税ではなく所得税を納めます。所得税の税率は、5%~45%まで、所得に応じて決まった金額を納めるものです。一方、法人の場合は法人税となり、税率は15%~23.2%まで(普通法人・2022年4月1日以後の場合)です。
個人事業主として太陽光発電事業を行っている場合、一定の収入を超えたときが、法人化を検討するタイミングでしょう。
参考:国税庁『No.2260所得税の税率』『No.5759法人税の税率』
法人として太陽光発電に取り組む準備を進めよう!
電気を自給でき、CO2削減や電気代高騰による自社へのリスクにも備えられる太陽光発電。中小企業にとって負担となる初期投資は、契約方式の工夫や、補助金制度の活用によって軽減することもできます。導入の際は、節税につながる優遇措置の認定条件などについても調べて、計画的に進めることが重要です。今回紹介した内容も参考に、自社に最適な取り入れ方を検討してみましょう。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。