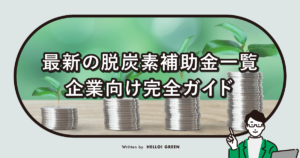企業の省エネ取り組み事例を厳選。効果的な対策と成功のポイント
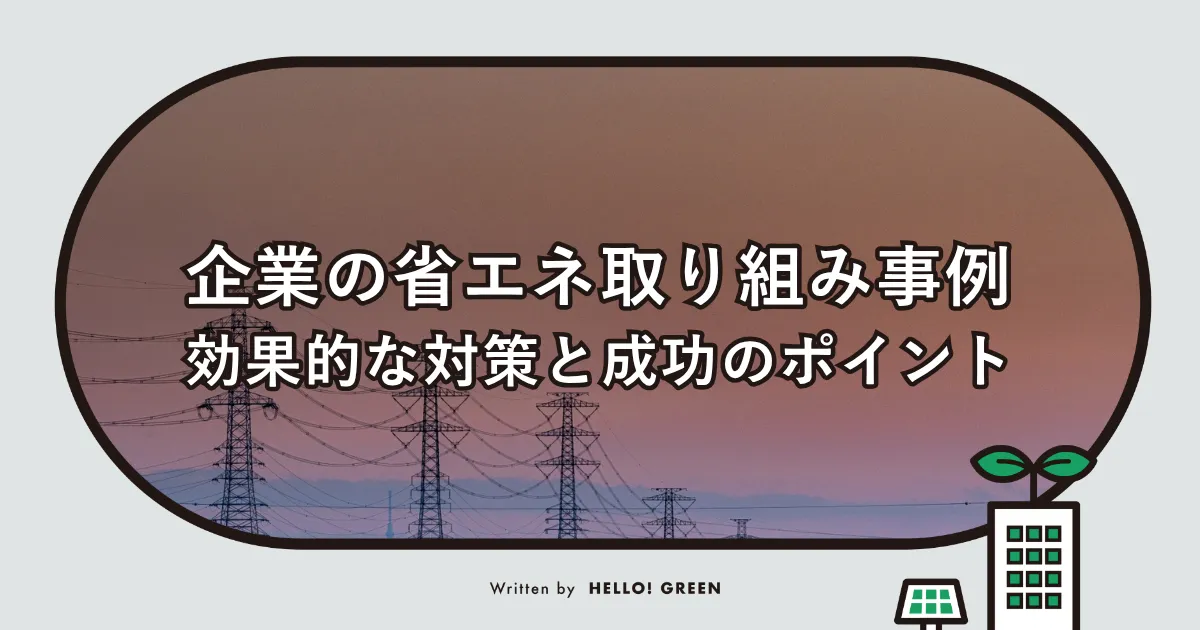
企業にとって「省エネ」は、地球温暖化を抑えるための社会的責任であり、電気代や燃料費の値上げに対応するための手段でもあります。今回は企業の環境担当者に向けて、工場やオフィスにおける具体的な取り組みを紹介します。また、省エネに取り組むべき理由、補助金制度、中小企業が省エネを成功させるポイントについても解説。省エネを強化し、企業価値向上へつなげる「中小企業版SBT」もあわせて紹介します。
HELLO!GREENでは脱炭素経営の進め方に悩む中小企業さまに向けたお役立ち資料をご用意しています。ぜひご活用ください。
→資料を無料ダウンロードする
- 社会的責任や、法規制・光熱費の上昇に対応するために、省エネは重要です。
- 省エネに活用できる補助金制度があります。
- 中小企業版SBTなどで自社の取り組みを可視化して、省エネを競争力強化につなげます。
【工場】省エネの取り組み例
省エネとは、「エネルギーの使用量を減らすこと」「エネルギーをより効率的に利用すること」を指します。製造業を中心とした工場はエネルギー使用量が大きく、省エネは生産コストの削減につながる重要課題です。ここでは、具体的な取り組み例をいくつか紹介します。
ポンプ・ファンのインバータ化
ポンプやファンは多くの電力を消費する設備で、これらにインバータを設置することで、大幅な省エネが期待できます。モーターの回転数を制御するため、必要に応じた能力で運転できるようになり、無駄な電力消費を抑えます。
エア漏れの検知と修理
圧縮空気設備からのエア漏れは、見逃されがちなエネルギー損失の原因です。小さなエア漏れでもエネルギーロスに直結するため、年間では大きな損失となる恐れがあります。無駄なコンプレッサーの稼働を抑えるために、エア漏れ箇所を定期的に検知・修理することで、省エネ効果を高めます。超音波式検知器などを用いて、効率的にエア漏れ箇所を特定することも大切です。
生産プロセスの見直し
生産プロセス全体を見直し、エネルギー効率のよい工程に改善することも重要です。例えば、連続生産への移行、熱源の統合、廃熱の再利用、乾燥工程の最適化などが挙げられます。無駄な工程をなくしてエネルギー使用量を減らすことで、省エネと同時に生産性の向上も期待できます。
エネルギー管理システム(EMS)の導入
エネルギー管理システム(EMS:Energy Management System)を導入して、エネルギーを「見える化」します。電力、ガス、水などのエネルギー使用量をリアルタイムで把握し、エネルギー効率の悪い部分を特定して、改善に役立てます。制御機能を持つEMSによって設備の稼働状況を最適化して、担当者の経験や勘に頼ることなく、効率的に省エネを進めることが可能です。
【オフィス】省エネの取り組み例
オフィスの電力消費は、空調・照明・OA機器などの使用によるものです。そのため、使い方の工夫や設備の見直しなどが中心になります。ここでは、従業員の快適性を維持しつつ、コスト削減と環境負荷低減を実現できる施策を紹介します。
オフィス機器の省エネモードの活用
パソコンやモニター、複合機などのオフィス機器には、省エネモード(スリープ機能)が搭載されています。待機電力の無駄を減らす機能を使うことで、使用していない間の電力消費を抑えることが可能です。例えば、退勤の際はモニターをオフにする、昼休みは複合機をスリープモードにするなど、小さな積み重ねがCO2削減につながります。
LED照明への更新
従来の蛍光灯や白熱灯をLED照明に更新することも、オフィスにおける効果的な省エネ策の1つです。LED照明は、従来の蛍光灯と比べ約40〜60%の電力削減が可能で寿命も長いため、電気代と交換の手間も低減できます。既存照明のLED化は、配線工事(バイパス工事)が必要なケースがありますので、更新の際は電気工事の専門業者へご相談ください。
空調の室外機のフィンの清掃
空調の運転効率を維持するには、室外機のフィン(熱交換器)の清掃が欠かせません。フィンにホコリや汚れがたまると熱交換効率が低下するため、手入れをして運転効率を維持し、無駄な電力消費を防ぎます。清掃の頻度や方法など、メーカーの推奨に従うことも大切です。
外気導入量の削減
空調において、必要以上に外気を取り込まないことも省エネにつながります。特に夏・冬は、外気の取り込みで冷暖房の負荷が増し、電力消費が無駄に膨らみがちです。換気はオフィスのCO2濃度に問題がない範囲にとどめて、外気の量を調整することで、空調にかかるエネルギー消費量を削減します。
【中小企業向け】SBT申請支援 割引キャンペーンはこちら>>
企業の省エネ取り組み事例
製造業や食品業、小売業など、業種を問わず多くの企業が省エネによるCO2排出量削減に取り組んでいます。ここでは、具体的な省エネ施策を実施した中小企業の事例を紹介します。補助金の活用も含め、自社の取り組みの参考にしてみてください。(補助金については、記事の後半で解説します。)
株式会社ニッコークリエート|高効率設備の導入で生産性と安全性が向上
株式会社ニッコークリエート(栃木県栃木市)は、主に鋳鉄・アルミ部品の設計・製造〜組み立てまでを一貫して行う産業機械メーカーです。従来の設備は、保持炉内壁へのアルミ付着により燃焼効率が低下し、生産が不安定でした。高効率設備の導入によって、CO2排出量がおよそ3割削減。付着除去作業の頻度が減ったことで生産性が向上し、作業負荷の軽減と安全面の改善にもつながったようです。
(参考:環境省『2023年度 エネルギー対策特別会計補助事業 活用事例集』p.62)
株式会社ヤヨイサンフーズ|燃料を転換してCO2排出量とコスト削減
業務用冷凍食品を製造・販売する株式会社ヤヨイサンフーズ(本社:東京都港区)は、環境省のSHIFT事業を活用して、老朽化した重油式ボイラーを都市ガス式の高効率ボイラーに更新しました。設備の効率化による省エネで、ランニングコスト削減も成功。さらに、重油から都市ガスになったことでばい煙が減少したため、地域環境が改善したそうです。
(参考:環境省『2023年度 エネルギー対策特別会計補助事業 活用事例集』p.114)
株式会社タイヘイ|設備更新とデータの遠隔確認で業務負荷も軽減
株式会社タイヘイ(本社:鹿児島県南さつま市)は、総合スーパーマーケットを営んでおり、県内事業所の老朽化した機器や設備を更新しました。加えて照明のLED化を行い、CO2排出量を年間約261トン削減、エネルギーコストを年間約899万円削減することに成功しました。また、同社は設備更新と同時に、メーカーと協力してエネルギーデータの遠隔確認が可能なシステムを導入。これにより、目視による確認やデータ整理にかかる業務負荷を軽減しながら、的確なデータ管理を実施しているそうです。
(参考:環境省『2023年度 エネルギー対策特別会計補助事業 活用事例集』p.146)
三陽金属株式会社|金属加工炉のDX化で休日・夜間運転を効率化
機械用刃物の製造・販売を行う三陽金属株式会社(兵庫県三木市)、巴第一工場において、環境省のSHIFT事業を活用し、省エネおよびCO2排出削減に取り組みました。同社は工場内で、金属加工炉の熱源が休日・夜間も連続して保温運転を行っており、電力消費量の削減が課題でした。
この課題に対し、ポータブル通信電流計を用いたDXシステムを導入し、各設備の電気使用量の測定や稼働監視を実施。不要な時間帯での温度保持停止が可能となったため、CO2排出量とエネルギーコストの削減に成功したほか、海外顧客に対して環境対策実施をアピールできる効果もあったようです。
(参考:環境省『令和5年度 SHIFT事業事例集』p.5)
大倉工業株式会社|ヒートポンプを導入して回収した熱をリサイクル使用
大倉工業株式会社(香川県丸亀市)の丸亀第5工場では、ボイラーの燃料に重油を使用していたため、大量のCO2排出が課題でした。設備更新を機に、ボイラーの燃料を重油から都市ガスへ転換。加えて、熱回収ヒートポンプを導入して回収したエネルギーをリサイクルすることで、CO2排出量とエネルギーコスト削減を実現しました。同社はグループ全体でCO2排出量削減を図っており、太陽光発電システムの導入、物流の効率化、単純焼却となる廃プラスチック削減など、さまざまな省エネ活動・環境対策を行っています。
(参考:環境省『令和5年度 SHIFT事業事例集』p.11)
なぜ企業にとって省エネが重要なのか?
企業にとっての省エネは単なるコスト削減だけでなく、事業継続のための経営戦略の1つです。重要とされる主な理由として、以下の3点が挙げられます。
省エネ法による規制と企業の責任
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」は、特定の企業(事業者)に対してエネルギー使用の合理化を義務づけています。対象企業は定期的な報告や削減目標の設定などが求められ、法令遵守と企業イメージ向上という観点から、積極的に省エネに取り組む必要があるでしょう。
(参考:資源エネルギー庁 省エネポータルサイト『事業者向け省エネ関連情報』)
省エネに対する企業の取り組み状況
昨今のエネルギー価格高騰は、企業の利益を直接的に圧迫しています。大企業はその膨大な電力使用量から影響を受けており、中小企業は高騰したコストを製品価格に転嫁するのは困難で、省エネの重要性はますます高まっています。
しかし、取引先からの脱炭素要請で対応が必要と考える企業は多い一方で、リソース不足で本格的な省エネに踏み出せない企業も少なくありません。
省エネに取り組むことによる経済的メリット。企業価値の向上にも貢献
省エネは、企業にさまざまな経済的メリットをもたらし、企業価値向上にも貢献します。
1.エネルギーコスト削減
最も直接的なメリットは、エネルギーコストの削減です。電気代や燃料費といったランニングコストは、企業の利益を圧迫する直接的な要因のため、これらのコストを抑えることで収益性を改善できます。
2.競争力強化
省エネへの積極的な取り組みは、企業の競争力強化にも役立ちます。エネルギー効率の高い生産プロセスやオフィス運営は、製造コストや運営コストの低減をもたらし、結果として製品やサービスの価格競争力の向上につながることがあります。
3.企業イメージ向上
さらに、省エネは企業のブランドイメージや社会的評価の向上につながります。一般社会の環境意識が高まり、環境に配慮する企業は消費者からの信頼を得やすく、人材採用にも好影響です。また、ESG投資の観点からも、省エネや脱炭素への取り組みは企業の持続可能性を示す重要な指標となり、資金調達の面でも優位に立つ可能性があります。
中小企業が省エネ対策を成功させるポイント
中小企業が省エネで成果を出すには、限られた資金で最大の効果を上げることが重要です。まず、現状分析とシミュレーションを念入りに行うことが不可欠です。どこで、どれだけのエネルギーが無駄に使われているかを把握し、対策後の効果を予測することで、費用対効果の高い施策を実施できます。
この際、「現場の勘」に頼るのではなく、科学的根拠に基づいた、現実的な目標を設定することが重要です。例えば、電力メーターのデータや設備ごとの稼働記録などを活用し、エネルギー消費の「見える化」を進めるなどです。自社だけでの分析が難しい場合は、外部の専門家に依頼するのも有効です。
また、設備やシステムの導入だけでなく、運用改善も省エネ効果を左右します。従業員への意識付けや、デマンド監視システムなどを活用した運用最適化も併行して進めることで、効率的な省エネを実現可能です。
省エネ対策に活用できる補助金制度
企業が省エネ対策を推進する上で、国や地方自治体などが提供する補助金制度を活用することが可能です。これらの制度は、初期投資の負担を軽減し、高額な省エネ設備の導入や改修を支援することを目的としています。主な補助金制度としては、以下のようなものが挙げられます。
●SHIFT事業(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業)
環境省が実施する、工場・事業場に脱炭素技術の導入を促進してバリューチェーン全体の脱炭素を図る事業です。「DX型CO2削減対策実行支援事業」と「省CO2型システムへの改修支援事業」の2本柱で、設備やシステムの導入・更新を計画している企業は、検討してみてもよいでしょう。
(参考:環境省『SHIFT事業』)
●省エネ補助金(省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金、省エネルギー投資促進支援事業費補助金)
経済産業省と環境省が管轄する事業で、一般社団法人環境共創イニシアチブが執行しています。「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」と「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の2種類をまとめて「省エネ補助金」と称しています。前者は工場・事業場全体の設備導入やエネルギー転換などを対象としており、上限額も高額です。後者は設備単体が主な対象で、中小企業の省エネ・脱炭素化を支援しています。
(参考:資源エネルギー庁『令和6年度補正予算「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」、「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の公募について』)
●ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業(東京都)
東京都が目指す「ゼロエミッション東京」の実現に向けて、中小企業の省エネルギー化を推進するための事業です。支援対象の例として、LED照明・高効率空調・断熱窓・高効率ボイラーといった省エネ設備や、人感センサー導入や照明スイッチ細分化工事のような設備運用を改善する費用が挙げられます。対象は都内の中小規模事業所で、先着順ではなく、期間中に予算を超過した場合は抽選となる点にご注意ください。
(参考:クール・ネット東京『ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業』)
省エネ対策を強化できる「中小企業版SBT」
中小企業版SBT(Science Based Targets)は、温室効果ガスの削減目標を科学的基準に基づいて設定する、国際的な認証制度です。省エネ対策と合わせてSBTを申請することで、エネルギー使用量やCO2排出量を定量的に分析し、自社の取り組みを見える化できます。
これにより、環境対応の進捗を社内外に効果的に示すことができ、競合との差別化や企業価値の向上、海外顧客へのアピールなどにつながります。中小企業版SBTは、通常版SBTよりも申請手続きが簡素化されており、省エネ活動を企業価値向上につなげる有効な手段といえるでしょう。
HELLO!GREENでは「中小企業版SBT認定を取得したいが、ノウハウが不足している」「対応できる人材がいない」とお困りの企業さまを支援しています。環境省認定「脱炭素アドバイザー」が、認定取得まで一気通貫でサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
企業の未来を見据えて省エネに取り組もう
企業が省エネに取り組むことは、社会的責任やコスト削減だけでなく、事業継続や競争力強化、そして企業価値向上に欠かせない経営戦略です。工場やオフィスで実践できる省エネは多岐にわたり、まずはエネルギー使用状況を見えるようにすることが大切です。そのうえで、LED照明化や高効率設備の導入、管理システムの活用など、効果的な取り組みから着手しましょう。国や自治体の補助金制度で投資負担を軽減しつつ省エネを強化するとともに、省エネ施策を活用する認証の取得も検討してみましょう。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。