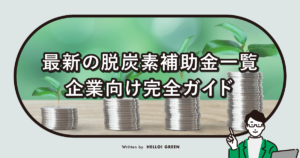建設現場のCO2削減方法。課題や具体的な取り組みなどを解説
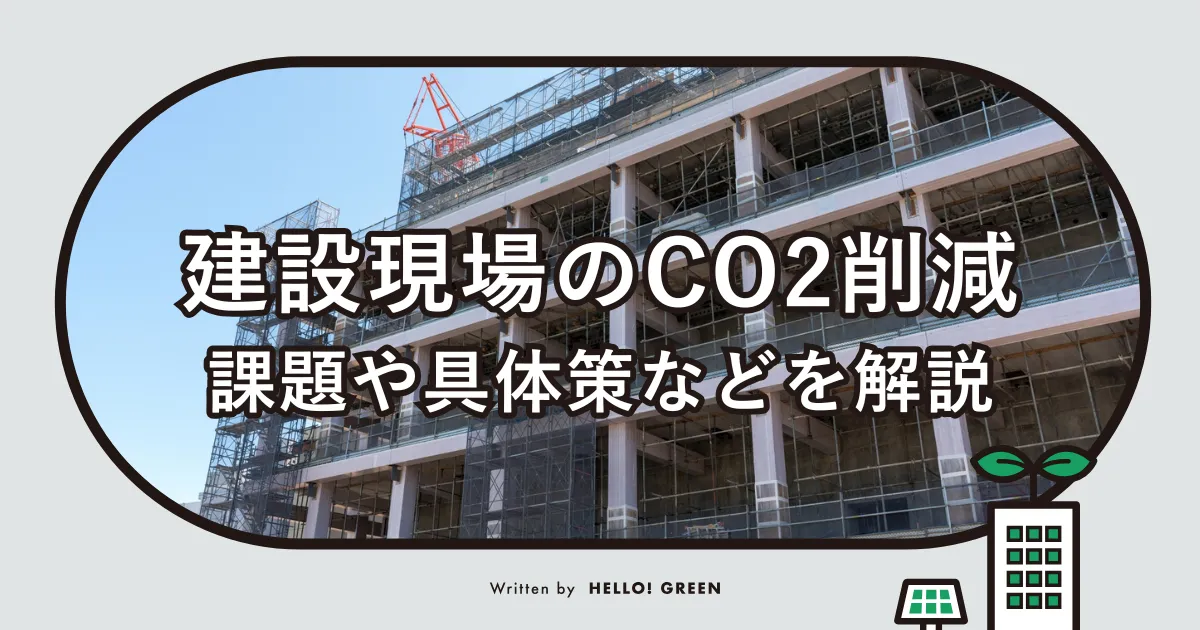
脱炭素経営の進め方がわかるお役立ち資料を無料ダウンロードをする
建設業界においても不可欠となっているCO2排出量の削減。単なる環境問題ではなく、取引先や親会社から排出量削減を求められるケースもあり、事業を継続していくうえで無視できないテーマとなっています。しかし、中小規模の建設企業にとっては、コストや人手不足などにより、どのように取り組むべきか悩ましい場合もあるでしょう。今回は、建設現場が無理なく取り組めるCO2削減策を解説しますので、脱炭素経営の第一歩として参考にしてください。
HELLO!GREENでは脱炭素経営を進める中小企業さまをご支援するために「中小企業版SBT認定」申請支援を行っています。環境省認定「脱炭素アドバイザー」が認定取得まで一気通貫でサポートいたします。ご興味をお持ちの方は、サービス資料をご覧ください。
→詳しいサービス資料をダウンロードする
- 事業継続や労働環境の悪化を防ぐためにも、建設現場のCO2削減は重要です。
- CO2排出量を可視化して明確な目標を示すことで、排出量を削減しながら自社の取り組みをアピールできます。
- 人手不足で対応できない場合は、外部サービスの活用も検討します。
建設業界におけるCO2削減の重要性
建設業界は、資材の製造や運搬、建設現場での工事、廃材の処分など、幅広いプロセスでCO2を排出する産業の1つです。そのため以下のような理由から、業界全体でのCO2削減が重要と考えられます。
1.排出量削減は建設業界としての責務
建設業を含む産業部門によるCO2排出は、日本の温室効果ガス(GHG)排出量の中でも大きな割合を占めており、削減は大手企業だけでなく中小企業も取り組むべき課題です。また、GHGの増加により地球温暖化が進むと、気候変動による自然災害の激甚化や猛暑日の増加などが発生し、これらは建設現場の工期遅延や労働環境の悪化といった悪影響をもたらします。
こうした背景から、業界全体でCO2排出量削減に取り組むことは、社会的な責務であると同時に、事業継続や安全な現場運営という側面からも重要です。
2.競争入札の加点対象
公共事業の入札において、企業の環境配慮への取り組みが評価される傾向が強まっています。脱炭素化の取り組みが競争入札で加点されることがあり、SBTなどを取得している企業や燃費性能に優れた建設機械を使用する企業は、有利になる可能性が高まります。
3.事業継続のための経営戦略
中小企業がCO2排出量を削減することは、自社が長く安定して事業を継続するための経営戦略でもあります。近年は、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の浸透や、サプライチェーン全体での脱炭素化の要求が高まり、環境対応の有無が企業評価に直結するようになっています。
投資家や金融機関は、企業の環境対策を投資判断の重要な基準としており、CO2削減に積極的に取り組む企業は、資金調達や企業価値の向上に有利な傾向にあります。また、省エネルギー化や脱炭素推進が光熱費削減につながれば、長期的なコスト削減が期待できます。
建設現場における主なCO2排出源
建設現場では、さまざまな活動からCO2が排出されます。主な排出源を把握することで、効果的な対策を検討できます。
建設機械や作業車両の燃料消費
建設機械や作業車両の多くは、ガソリンやディーゼルを燃料とするため、直接的にCO2を排出します。特に、稼働台数が多い工事や長期プロジェクトでは、それだけ排出量も多くなります。近年は電動化・低炭素化が進められているものの、高額なことや供給体制などが課題で、業界全体では不十分というのが実情です。
発電機の使用
近くに電線がない現場などでは、発電機を使って電源を確保することがあります。これらの発電機もガソリンなど化石燃料を燃焼させるため、CO2を直接排出します。
例えば、仮設事務所に太陽光発電システムを設置するなど、再生可能エネルギーを導入する現場は増えています。しかし、数カ月で完了するような工事で使用するのは初期費用と採算が合わず、設置と撤去の手間も課題です。「電力量が少ない」「太陽光パネルを置くスペースがない」など、再生可能エネルギーの使用が現実的でない場合もあります。
資材運搬・搬入時の輸送
建設に必要な資材は、工場や倉庫から現場まで、トラックや建設資材専用の大型車両などで輸送されます。この輸送過程においても、ディーゼルなど燃料の使用によるCO2が排出されます。輸送距離や輸送量、車両の種類などが排出量に影響し、例えばセメントや鉄骨のような重量物を長距離輸送する場合には、より多くのCO2が排出されることになります。
廃材の処理
建設現場で発生する廃材(木材・コンクリート・金属など)の処理でもCO2が発生します。例えば、木材など可燃物を焼却処理する際は、燃焼の過程でCO2が排出されます。CO2以外のGHGが発生する場合でも、全て「CO2換算」で排出量に含まれるため、結果としてCO2排出と同じように扱われます。
中小規模の建設企業が直面する課題と解決策
CO2削減の重要性は理解していても、中小規模の建設企業には特有の課題があり、対応が難しい場合もあるでしょう。ここでは、それらの課題と取り組みやすい施策について解説します。
専任の担当者がいない
中小企業の場合は、大企業のように環境対策専門の部署や担当者を配置することが難しく、CO2削減に関するノウハウや人材が不足している場合があります。工程や現場の管理に忙しく、脱炭素にまで手がまわらないという企業も多いでしょう。
この場合は、外部のコンサルタントや支援サービスを活用することで、担当者の負担を軽減しながら、専門的な知識や具体的なアドバイスを得ることが可能です。また、環境省や業界団体の公開資料などを活用すれば、コストをかけずに最新情報を効率よく収集できます。施策をスムーズに進めるために、従業員向けの研修を実施して、現場の意識向上を図ることも大切です。
ツールや測定方法が分からない・高額という不安
CO2排出量を把握するためには、適切なツールや測定方法が必要となりますが、導入コストが高い、専門知識が必要などで、ツール導入をためらうケースがあります。
こうした場合は、まず電気や燃料の使用量から排出量を算出するなど、簡易的な方法から実施しましょう。いきなり高機能なシステムを導入するのではなく、基本的なツールから段階的にステップアップすることも、費用負担の軽減につながります。補助金や税制の優遇措置を活用できれば、初期コストを抑えたCO2削減が期待できます。
(参考:環境省『排出原単位データベース』)
数値化しても活用できない
CO2排出量の数値で「見える化」できても、「どのように具体的な行動へつなげるか分からない」という場合もあります。数値データを行動変容につなげるためには、現実的な削減目標を設定し、数値を行動計画に落とし込むことが重要です。
さらに、定期的な進捗確認と改善のPDCAサイクルを実施することで、継続的な削減努力が可能になります。SBTのような認証制度を活用して、科学的根拠に基づく現実的な目標を設定することも、有効なアプローチです。
【中小企業向け】SBT申請支援 割引キャンペーンはこちら>>
建設現場でできるCO2削減策
大規模なシステムなどを導入しなくても、日々の業務の中で無理なく取り組めるCO2削減策はあります。ここでは、中小建設業で取り組みやすいCO2削減策を紹介します。
重機や車両の省エネ化
建設現場で使用する重機(建設機械)や車両の使い方を工夫して、大きなコストをかけずにCO2排出量を削減します。具体的な取り組みとして、以下が挙げられます。
●アイドリングストップの徹底
作業の合間や待機時間には、エンジンを停止するよう徹底しましょう。燃料消費を抑え、CO2排出量削減に貢献します。
●エコドライブの実践
乗用車と同様に、急発進・急加速・急ブレーキを避けるエコドライブが有効です。作業中でもアクセルを踏み込んだ状態で待機せず、掘削量や荷重に応じた出力調整を行うことで、無駄な燃料消費を抑えてCO2排出量を削減します。
●適切なメンテナンスの実施
エンジンオイルやエアフィルターの定期交換、タイヤ空気圧の管理など、日常的なメンテナンスも大切です。機械の性能低下や燃費悪化を防ぐことが、CO2の排出削減につながります。
●低燃費・高効率な機種の導入
車両や機械の更新時期には、省エネ性能に優れた新型モデルや、ハイブリッド型・電動型の建設機械の導入を検討しましょう。補助金や税制の優遇などを活用できれば、導入コストの軽減が期待できます。
電力使用量の抑制
建設現場に設置する仮設事務所の電力使用も、CO2排出の要因となります。LED照明や高効率なエアコンを導入するなどで、消費電力を削減しましょう。使用していない照明や電気機器はこまめにスイッチを切る、夏季・冬季の室温設定を適切にするなども大切です。
廃材の削減と分別の徹底
建設現場から発生する廃材の量を減らし、適切な分別・再資源化を行うことは、CO2排出量の削減と資源の有効活用につながります。以下のような取り組みを検討しましょう。
●プレカット工法の採用
構造材(柱・梁など)をあらかじめ工場で加工する「プレカット工法」を採用することで、現場で発生する廃材を削減します。また、内装材や配管などについても、プレカットと同様に工場で事前に加工したものを現場に搬入することで、現場での切断や調整作業による廃棄物の発生を抑制できます。これにより現場作業の効率化と、廃材処理コストの低減も見込まれます。
●3Rの推進
廃材の発生抑制(リデュース)、再利用(リユース)、再資源化(リサイクル)を意識した管理も、CO2排出削減方法の1つです。廃棄物の削減と適切な管理は、環境への配慮と同時に、建設業の社会的責任としても重要です。
例えば、仮設資材のリユース、分解可能な部材のリサイクルなどにより、廃棄処理で発生するCO2排出を削減します。「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に基づき、現場に「分別ヤード」を設ける場合もあります。
(参考:e-Gov 法令検索『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』)
協力会社との連携による効率化
建設現場は、資材調達や輸送、専門工事など、多くの工程を協力会社と連携して進めます。これらの工程を効率化することで、CO2排出量の削減につなげます。
●共同での資材調達
近隣現場や取引先と資材をまとめて調達することで、トラックの往復回数を減らし、輸送による燃料消費とCO2排出量を抑えます。
●輸送ルートの最適化
協力会社と配送ルートやスケジュールを調整することで、空車や遠回りを防ぎ、移動距離・時間・燃料使用の削減を図ります。
●工程管理の最適化
施工工程を見直し、作業の重複や手戻りを減らします。建設機械や設備の稼働時間を短縮することでエネルギー使用を抑制して、CO2排出量を削減します。
CO2削減のための外部サービス活用
リソース不足などにより自社だけでCO2削減に取り組むのが難しい場合は、外部の支援サービスを活用することも有効です。例えば、CO2排出量の算定を専門の事業者に依頼すれば、自社ではGHG排出量データを収集して提出するのみで、通常業務への影響を最小限に抑えられます。
そして、CO2削減の取り組みを対外的に示す手段として、国際認証制度である「中小企業版SBT」の取得を検討するのも一つの方法です。簡易な申請プロセスを通じて、科学的根拠に基づく現実的な削減目標を設定することが可能で、取引先や顧客に対しても脱炭素への真摯な姿勢をアピールできます。
HELLO!GREENでは、脱炭素経営を進める中小企業さまのために、「中小企業版SBT」の申請支援を行っています。環境省認定「脱炭素アドバイザー」が認定取得まで一気通貫でサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。
建設現場のCO2削減は「できることから」「見える化」して進めよう
建設現場におけるCO2削減は、環境への配慮だけでなく、自社の信頼性や事業継続に関わる重要な経営戦略でもあります。近年はどの産業でも、サプライチェーン全体でのCO2排出量の把握・削減が求められる傾向にあり、建設業も元請や発注者から排出量の報告や削減方針の提示が求められる可能性があります。
リソースに制限がある中小規模の建設企業は、大規模な投資ではなく、まずは排出量の可視化から始めることが、現実的な第一歩でしょう。日々の業務の中でできることを積み重ねていくことが、継続的な排出量削減につながります。
環境に配慮した現場づくりは、企業としての社会的責任だけでなく、公共工事など新たな受注機会にもつながる可能性があります。まずは、自社の排出状況を可視化し、実行可能な削減目標を検討するところから始めてみてはいかがでしょうか。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。