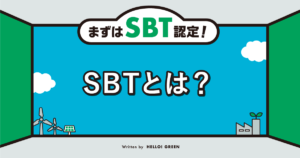【企業必見】SBTとエコアクション21の違いをわかりやすく解説

環境経営を推進したい企業のご担当者さまの中には、「SBTとエコアクション21はどう違うのか」を知りたい方も多いでしょう。「すでにエコアクション21の認証を受けているが、SBT認定も取得したほうがよいのか」も気になるところです。
この記事では、SBTとエコアクション21の違いをわかりやすく解説します。これを読めば、「どちらが自社に向いているか」「両方とも取得すべきか」を判断するのに役立つでしょう。
HELLO!GREENでは、「まずは情報収集から始めたい」「気になることを気軽に相談したい」という方に向けて、どなたでもご利用いただけるサポートをご用意しています。オンラインでの「無料相談会」も開催していますので、ぜひご活用ください。
- SBTとは、企業が設定した目標が、SBTイニシアチブ(SBTi)により科学的に妥当と認定された温室効果ガス削減目標のこと。一方、エコアクション21とは総合的な環境マネジメントシステムのことです。
- 両者の一番の違いは、「地球温暖化に特化しているかどうか」です。この他にも、いくつかの違いがあります。
- 企業によっては、SBTとエコアクション21の両方を取得するのも有効です。自社の現状を把握した上で、何を取得すべきかを決めましょう。
SBTとエコアクション21の違い
SBTとエコアクション21にはどのような違いがあるのでしょうか。それぞれの概要や両者の違いについて、わかりやすく紹介します。
SBT|企業が設定する温室効果ガス排出削減目標
SBT(Science Based Targets、直訳:科学的根拠に基づく目標)とは、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標のこと。温室効果ガス(GHG、Greenhouse Gas)の排出を抑え、地球温暖化を抑制することを目的としています。
国際的な気候変動対策の枠組みである「パリ協定」と整合した目標で、世界の気温上昇を1.5℃未満に抑えるために必要な削減量が基準となります。単なる自主目標ではなく、自社の温室効果ガス排出量を正確に把握した上で目標を設定し、その妥当性について国際的な認定機関(SBTi)の審査を受けます。
エコアクション21|総合的な環境マネジメントシステム
エコアクション21は、事業者の環境パフォーマンス向上を目的とした、環境マネジメントシステムです。「環境パフォーマンス」とは、企業などが環境方針や目標に基づいて活動した結果として得られる、環境への影響を示す測定可能な指標のこと。エコアクション21ではCO2排出量、水使用量、廃棄物排出量の3点が、「必ず把握すべき項目」として規定されています。加えて、「必ず取り組む行動」として、次の4点が定められています。
■必ず取り組む行動
- 省エネルギー
- 廃棄物の削減・リサイクル
- 節水
- 企業が生産・販売・提供する製品の環境性能の向上およびサービスの改善
企業などの事業者は、自身の事業活動と環境負荷との関係に気づき、これらの指標を把握・改善して、環境負荷を軽減することが求められます。目標についてSBTのような統一基準はなく、業種や規模に応じて、各社が実行可能な範囲で設定します。
一番の違いは、地球温暖化に特化しているかどうか
SBTとエコアクション21の一番の違いは、取り組みの目的が「地球温暖化」に特化しているか、より広く環境問題を捉えているかです。
SBTは、温室効果ガス削減に特化した制度です。一方、エコアクション21は、地球温暖化抑制のみならず、水資源の保全や廃棄物量の削減など、幅広い環境課題に対応する総合的な取り組みです。そのため、温室効果ガス削減だけでなく、日常的な環境配慮や法令順守の体制整備なども含め、企業の環境活動全般を改善することで環境負荷の軽減を図ります。
どちらが自社に向いている?5つの違いを比較
「地球温暖化に特化しているかどうか」以外にも、SBTとエコアクション21にはいくつかの違いがあります。ここでは、「目標設定の根拠」「対象範囲」「社会的な認知度」「取得の難易度」「取得費用」の5つについて、違いを比較します。
「どちらが自社に向いているのか」を判断する際のヒントとして、お役立てください。
目標設定の根拠
| SBT | エコアクション21 |
|---|---|
| パリ協定と整合した目標 | 環境省が策定したガイドライン |
SBTは、パリ協定に沿った温室効果ガス削減目標で、科学的根拠に基づいた明確な削減目標が求められます。これに対しエコアクション21は、事業活動による環境負荷の軽減と経営の改善を目的として、各企業が柔軟に目標を設定します。
対象範囲
| SBT | エコアクション21 |
|---|---|
| サプライチェーン全体 | 事業活動全般 |
SBTで対象となる温室効果ガスは、自社による排出だけでなく、原材料や製品の輸送、廃棄、従業員の出張など、サプライチェーン全体にわたる排出が含まれます。エコアクション21では、主に自社の事業活動に伴う環境負荷が対象となっています。
社会的な認知度
| SBT | エコアクション21 |
|---|---|
| 国際的に知名度が高い | 国内での知名度は高い |
SBTはグローバル・スタンダードであり、海外企業やグローバルサプライチェーンとの取引において高い評価を得られる、国際的な認証制度です。SBT認定を取得している大企業と取引がある中小企業も、同様の取り組みを求められるケースが増えています。
一方のエコアクション21は、環境省が策定した環境マネジメントシステムの一種です。パリ協定が採択される以前からある制度で、中小企業でも取り組みやすいため、取得企業は多いです。ただし国内規格のため、国際的な知名度はSBTほど高くありません。
取得の難易度
| SBT | エコアクション21 |
|---|---|
| 比較的難しい | 取得しやすい |
SBTは、温室効果ガス排出量の詳細なデータ収集と継続的な報告が求められます。厳格な基準があり、対応するための社内体制や専門知識が必要になるため、外部コンサルタントなどの支援を受ける企業も少なくありません。ただし、中小企業向けに手続きが簡素化された「中小企業版SBT」は、排出量の対象が自社の事業活動と電気・ガスなど燃料使用に限定されており、申請フォームも簡易なため、通常版よりも導入しやすくなっています。
国内の制度であるエコアクション21は、日本語のマニュアルがあり、内部監査が要求事項ではないため(一部例外あり)、難易度は低めです。地域の事務局(2025年5月時点で27都道府県、34団体)で相談可能で、初めて環境認証を検討する企業にとって取り組みやすい制度と考えられます。
取得費用
| SBT | エコアクション21 |
|---|---|
| 高額になる傾向(為替相場により変動) ・通常版SBT:11,000米ドル ・中小企業版SBT:1,250米ドル | 業種や従業員数で変動 |
SBTの方が、エコアクション21よりも高額な傾向にあります。通常版SBTの申請では11,000米ドル、中小企業版SBTでは1,250米ドルが必要で(2025年5月時点)、申請料のほかに為替手数料や海外送金の手数料もかかります。エコアクション21の費用は「標準審査工数表」によって決められており、業種や従業員数で異なりますが、比較的低額です。
いずれの場合も、自治体が脱炭素を促進する目的で、補助金など優遇制度を設けていることがあります。申請費用のほか、手続きを外部に委託した際の代行費用を補助する自治体もあるため、自社の地域の制度を調べてみるとよいでしょう。
【中小企業向け】SBT申請支援 割引キャンペーンはこちら>>
SBTとエコアクション21を両方取得するという選択肢も
両者はそれぞれ特徴が異なるため、企業によってはどちらか1つに限定せず、両方の取得を検討してみるとよいでしょう。SBTは海外取引の拡大に、エコアクション21は地域密着型企業のCSR強化にそれぞれ適しており、両方を取得することで「国際的な信頼性」と「国内での環境経営レベルの向上」の両立が期待できます。SBTの申請手続きを自社のみで対応するのが難しい場合には、手続きを外部に委託することで、担当者の業務負荷を減らしながらスムーズな申請が可能です。
■中小企業版SBT認定の取得に関してハードルを感じていませんか?
- ノウハウがない
- リソースが限られており対応できる人材がいない
- 海外とのコミュニケーションが不安
HELLO!GREENでは、環境省認定「脱炭素アドバイザー」が面倒な作業を代行。認定取得まで一気通貫で支援いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
詳しいサービス資料をダウンロードする>>
SBTとエコアクション21は、どちらも企業にとって重要
SBTとエコアクション21は、それぞれ異なる目的と特徴を持つ認定制度ですが、いずれも企業にとって持続可能な経営を実現するために必要です。SBTは、企業の排出目標が科学的根拠に基づいていると認められることで、サプライチェーンからの信頼を得られる制度です。
取引先の大企業や海外企業からの評価が高まるという点で、今後の事業展開にも影響を与えるでしょう。一方、エコアクション21は、電力や廃棄物の管理など、企業活動全体の環境負荷を総合的に見直す制度です。柔軟な目標設定が可能なため、環境マネジメントの入門として位置づけることもできます。
いずれを採用する場合でも、両者の違いを正しく理解し、自社の現状や今後のビジョンに合わせて選択することが重要です。企業によっては、両方の取得を検討したほうがよい場合もあるので、まずは自社の状況を整理し、専門機関に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。