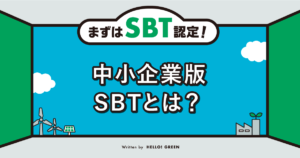【最新版】カーボンニュートラル燃料の特徴とは?価格や関連企業の動向など
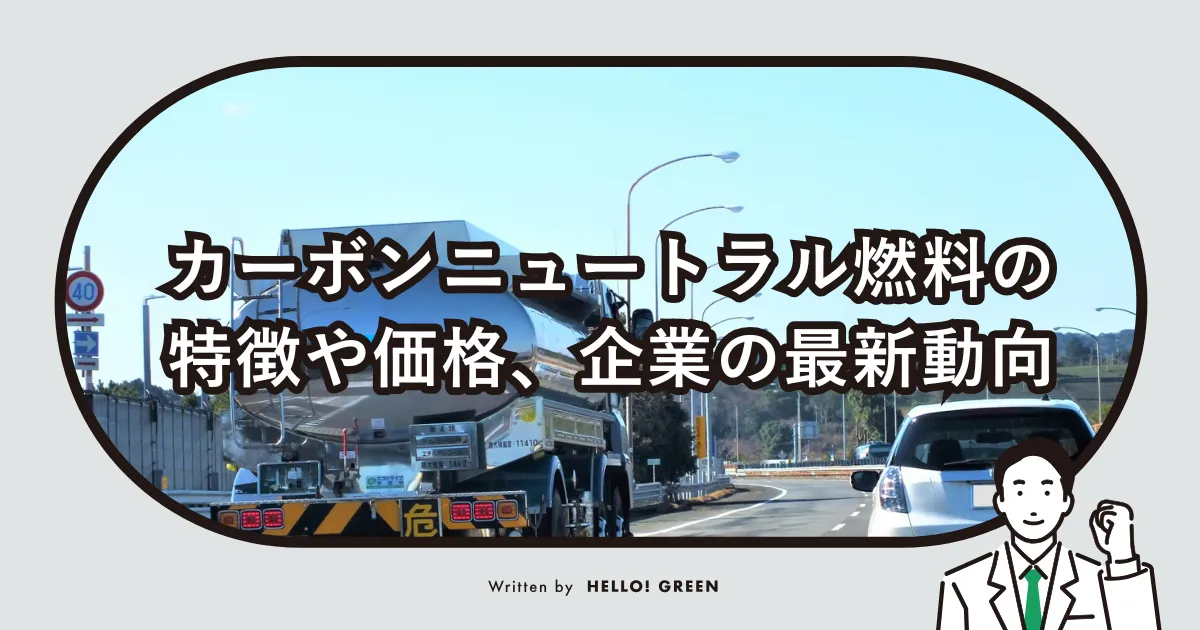
脱炭素経営の実現に向けて、ガソリンなどの化石燃料に代わるものとして注目されているカーボンニュートラル燃料(CN燃料)。しかし、その導入にはコストや技術的な課題も存在します。
今回の記事では、カーボンニュートラル燃料の基礎知識も交えながら、技術の将来性や各業界の導入に向けた最新情報を紹介します。
HELLO!GREENでは脱炭素経営の進め方に悩む中小企業さまに向けたお役立ち資料をご用意しています。ぜひご活用ください。
→資料を無料ダウンロードする
- カーボンニュートラル燃料とは、燃料を作る、運ぶ、燃焼させるといった、一連のライフサイクルにおいてCO2排出量を抑えられる燃料の総称です。
- 合成燃料やバイオ燃料が主な種類で、技術開発やコスト削減が課題となっています。
- カーボンニュートラル燃料の一つである「合成燃料」の取り組みでは、2040年の商用化を目標に進められているプロジェクトもあります。
カーボンニュートラル燃料(CN燃料)とは?
カーボンニュートラル燃料とは、CO2排出を抑えられる、環境にやさしい燃料の総称です。その定義や意味についてみていきましょう。
製品ライフサイクル全体において「CO2排出量を抑えられる燃料」
カーボンニュートラル燃料とは、燃料を作る、運ぶ、燃焼させるといった、一連のライフサイクルにおいてCO2排出量を抑えられる燃料を意味します。CO2と水素から作られた「合成燃料」や、植物などを原料にした「バイオ燃料」が、カーボンニュートラル燃料に該当します。
エンジン車もカーボンニュートラル燃料を使用すればCO2排出が実質ゼロ
カーボンニュートラル燃料の一つである合成燃料は、エンジン車の代替燃料として利用できます。合成燃料も、ガソリンと同じように燃焼時にCO2を排出しますが、CO2を回収して製造されているため、ライフサイクル全体でのCO2排出量が実質的にゼロとみなされるのです。
カーボンニュートラル燃料の種類
カーボンニュートラル燃料の種類や違いについて紹介します。
| 合成燃料 | バイオ燃料 |
|---|---|
| 水素とCO2を化学反応させて作られる人工的な燃料 | 植物や動物由来の有機物(バイオマス)から作られる燃料 |
| ・e-fuel ・合成メタン など | ・バイオエタノール ・バイオディーゼル など |
「e-fuel」とは、水素を取り出す過程などで再生可能エネルギーを使っている燃料です。合成燃料の多くは液体燃料ですが、メタンを合成して作られた「合成メタン」は気体燃料です。
「バイオエタノール」などは、そのまま燃料として使用する方法のほか、ガソリン混合燃料として利用する方法もあります。
カーボンニュートラル燃料のメリット・デメリット
カーボンニュートラル燃料の一つである合成燃料のメリットは、車両やガソリンスタンドなどの既存インフラを活かせることです。一方、製造コストがかかるため価格が高くなることがデメリットでしょう。それぞれについて解説します。
メリット|カーボンニュートラル燃料は既存インフラで利用可能
メリット
・CO2排出量の削減
・日本のエネルギー自給率の向上
・既存インフラで利用可能(合成燃料)
CO2排出量を削減するために電気自動車も普及し始めていますが、多くの企業において、すべてを電化するのは難しいのが現状です。合成燃料は、化石燃料と同等の高いエネルギー密度をもち、既存の車両やインフラをそのまま使いながら、脱炭素化できることがメリットです。
カーボンニュートラル燃料が普及すれば、国内でのエネルギー自給率向上が期待でき、エネルギーの安定供給にもつながります。
デメリット|カーボンニュートラル燃料の価格。低コスト化が課題
デメリット
・製造コストがかかる
・原料の供給量に限りがある
カーボンニュートラル燃料は、ガソリンなどと比べて製造コストが高いことがデメリットです。合成燃料の場合、生産コストが約300円~700円/Lかかると試算されています※1。
バイオ燃料の一つである「バイオディーゼル」の場合、一部の研究によると、生産コストが現状で107円/Lかかっており、今後平均3.5円/Lほど減少する見込みです※2。価格を低減化してバイオディーゼルを普及させるには、炭素税導⼊やバイオディーゼル燃料への税⾦引き下げが必要だとする見解も示されています。
バイオ燃料は、原料となる植物の供給量や土地利用の制約も課題の一つです。解決に向けて、廃棄物の活用や新たな栽培技術の開発が進められています。
脚注
※1:資源エネルギー庁『合成燃料(e-fuel)の導入促進に向けた官民協議会中間とりまとめ(案)』海外ですべて製造し輸入すると300円/L、国内で原料調達から製造まで行うと700円/Lと試算。ただし、水素の価格によって異なる
※2:九州大学『国内バイオディーゼル燃料製造事業 現状打開の糸口を探る!』九州⼤学の研究グループが、⽣産理論(経済学)に数理最適化モデルを応⽤した独⾃の研究フレームワークに基づき調査・分析したもの。2023年発表
カーボンニュートラル燃料はいつから実用化される?
すでに導入され始めているバイオ燃料は、ガソリンへの混合利用などが行われています。合成燃料の場合は、2040年までに自立的な商用化を目標とする国の計画が進行中です。
実用化に向けた技術開発や体制構築、低コスト化といった取り組みを支えるため、国の戦略の一つ「水素基本戦略」が2023年6月に改定。水素に加えて、合成燃料も研究開発の対象として拡大する意向が示されています。
各業界のカーボンニュートラル燃料導入の動き
カーボンニュートラル燃料の導入に向けた、各業界の動きについて紹介します。
自動車メーカーを含む4社が共同で取り組みを検討
2024年5月、トヨタ自動車株式会社、出光興産株式会社、ENEOS株式会社、三菱重工業株式会社は、カーボンニュートラル燃料の導入に向け、4社が共同で取り組むことを発表しました。「導入のロードマップや必要な制度」「製造の実現可能性」などを共同で検討していく方針です。
自動車業界では、次世代燃料としてさまざまな種類のカーボンニュートラル燃料が候補に挙がっていますが、コスト面などで課題も多いのが実情です。4社共同での取り組みが業界にどのような進展をもたらすのか、今後の動向が注目されます。
航空業界ではSAF(持続可能な航空燃料)導入に向け体制構築
廃油やバイオマスなどの資源から作られる、次世代の航空燃料「SAF」。既存の航空機やエンジンを活用しながら、CO2排出量を大幅に削減できる点がメリットです。SAFの導入に向け、国は2030年までにジェット燃料の10%をSAFでまかなう目標を立てています。
これを受けて、出光興産株式会社ではバイオ原料を用いたSAFを、年間50KL供給できるような体制を構築するためのプロジェクトが進行中。SAFの実用化には、さらなる技術革新や産業間連携が求められており、原料供給の安定化やコスト削減が課題です。
コンビニで廃油回収。配送トラックの燃料に活用する実証実験
カーボンニュートラル燃料の導入に向けた実証実験が、身近なところでも進められています。2024年12月、コンビニで回収した廃油を配送トラックの燃料に活用する試みが開始されました。
このプロジェクトに連携して取り組んでいるのは、株式会社セブン-イレブン・ジャパンや三井物産株式会社などを含む5社。陸上輸送の脱炭素化を実現する有力な手段として、バイオディーゼル燃料の活用を目指しています。
参考:PR TIMES『出光興産、ENEOS、トヨタ自動車、三菱重工業、自動車向けカーボンニュートラル燃料の導入と普及に向けた検討を開始』『バイオディーゼル燃料100%を活用したセブン-イレブン店舗への配送を開始』
参考:経済産業省『出光のカーボンニュートラル(CN)への取組みについて』
参考:資源エネルギー庁『CN燃料普及のあり方について』
脱炭素経営を企業価値の向上につなげる「中小企業版SBT」
多くの企業がカーボンニュートラル燃料を導入することで、脱炭素経営の実現だけでなく、社会からの信頼向上にもつながると考えています。社会的評価を高める有効な手段として、「中小企業版SBT(Science Based Targets)」の取得も挙げられます。
SBTとは、パリ協定の目標達成に向けた企業の温室効果ガス削減目標を設定するものです。国際的なイニシアチブである「Science Based Targets initiative(SBTi)」によって認定されるため、社会的な信頼性が高く、競合他社との差別化にも貢献するでしょう。
HELLO!GREENでは脱炭素経営を進める中小企業さまをご支援するために「中小企業版SBT認定」申請支援を行っています。環境省認定「脱炭素アドバイザー」が認定取得まで一気通貫でサポートいたします。ご興味をお持ちの方は、サービス資料をご覧ください。
→詳しいサービス資料をダウンロードする
動向をチェックしながら、カーボンニュートラル燃料の導入も検討しよう!
カーボンニュートラル燃料は、脱炭素社会の実現に向けた有力な選択肢の一つですが、価格や原料の安定供給など、多くの課題が残っているといえるでしょう。こうした状況を打開するために、企業連携や国の政策支援が積極的に進められています。各業界の動向をチェックしながら、カーボンニュートラル燃料の導入も含め、脱炭素に向けた計画をブラッシュアップしていきましょう。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。