基礎排出係数と調整後排出係数の違いは?選ぶ基準もわかりやすく解説
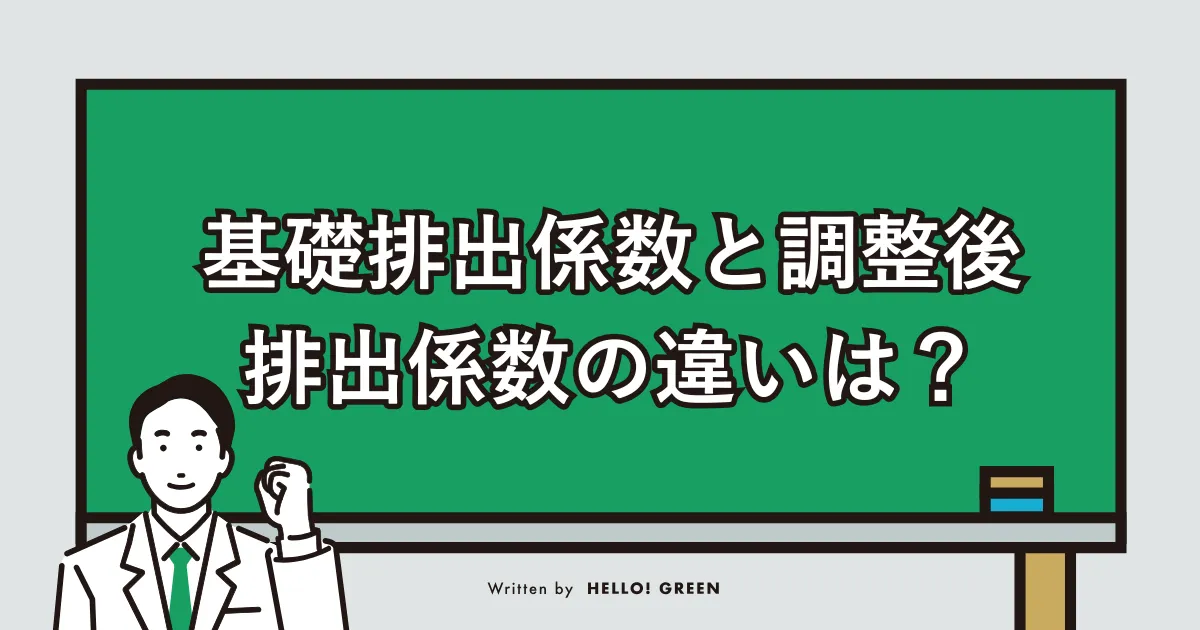
HELLO!GREEN の「中小企業版SBT認定申請サービス」資料を無料ダウンロードする
CO2排出係数には、「基礎排出係数」と「調整後排出係数」の2種類があります。自社の温室効果ガス排出量の算定に取り組み始めた企業では、「なにが違う?」「どちらを選ぶべき?」などの疑問を抱えていることも少なくありません。
今回は、CO2排出係数の基本や、基礎排出係数と調整後排出係数の違いをわかりやすく解説します。排出量を算定する際に誤りがないよう、しっかりポイントを押さえておきましょう。
HELLO!GREENでは「中小企業版SBT認定を取得したいが、ノウハウが不足している」「対応できる人材がいない」とお困りの企業さまを支援しています。環境省認定「脱炭素アドバイザー」が認定取得まで一気通貫でサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
→詳しいサービス資料をダウンロードする
- 基礎排出係数は、発電に伴うCO2排出量を1kWh使用当たりで示した値です。
- 調整後排出係数は、実際の排出量に基づき、電力会社によるCO2削減の取り組みを反映させて調整し、1kWh使用当たりで示した値です。
- 法定報告では、基礎排出係数と調整後排出係数の両方で算定した結果が求められる場合があります。
CO2排出係数とは
「CO2排出係数」とは、エネルギーを作る過程における活動量当たりのCO2排出量を示す数値のことで、電力、ガス、燃料使用時などの排出量算定に使います。
CO2排出係数の例
・電力1kWh当たりのCO2排出量
・ガス1千m³当たりのCO2排出量
例えば電力なら、電気事業者ごとにCO2排出係数が発表されます。これをもとに電力を購入している企業は、自社の電力使用量に応じた排出量を算定します。
CO2排出係数を用いた計算例
自社の電力使用量×契約している電力メニューのCO2排出係数=自社の電力使用による間接的な温室効果ガス排出量
※排出量の算定には複数の方法があり、上記は一例です
環境省のホームページに、電気事業者別排出係数一覧が掲載されています。
基礎排出係数と調整後排出係数の違い
CO2排出係数には、基礎排出係数と調整後排出係数の2種類あります。どちらも温室効果ガスの排出量を算定するための係数ですが、その算定方法には次のような違いがあります 。
| 種類 | 基礎排出係数 | 調整後排出係数 |
|---|---|---|
| 算定方法 | 発電時のCO2排出量を販売した電力量で割った数値 | 基礎排出係数に、環境負荷を低減する取り組み(非化石証書の調達など)を反映した数値 |
| 意味 | 発電に伴うCO2排出量を1kWh使用当たりで示したもの | 排出量の削減努力を考慮した実質的なCO2排出量を、1kWh使用当たりで示したもの |
それぞれ詳しくみていきましょう。
基礎排出係数の計算方法
基礎排出係数は、電気事業者が発電の際に排出したCO2排出量を、その事業者が販売した電力量で割った値です。発電に伴うCO2排出量を表すもので、再生可能エネルギーの活用などによる排出量削減の取り組みは反映されていません。
基礎排出係数は、以下のような計算方法で算定されます。
基礎排出係数=発電時の二酸化炭素排出量(t-CO2)/販売電力量(kWh)
調整後排出係数の計算方法
調整後排出係数は、実際の排出量に基づいて調整した排出係数です。特定の制度によるカーボン・オフセットなど、電力会社がさまざまな取り組みによって削減したCO2の排出量を反映させた値です。基礎排出係数と比べて、より実質的なCO2排出量を示しているといえるでしょう。
調整後排出係数は、以下のような計算方法で算定されます。
調整後排出係数=【基礎二酸化炭素排出量(t-CO2)+再生可能エネルギーの固定価格買取制度に関連して二酸化炭素排出量を調整した量(t-CO2)-クレジット使用などによりカーボン・オフセットした二酸化炭素排出量(t-CO2)】÷販売した電力量(kWh)
【中小企業向け】SBT申請支援 割引キャンペーンはこちら>>
基礎排出係数と調整後排出係数のどちらを選ぶべきか
| 使用目的 | 推奨される排出係数 |
|---|---|
| 企業の自主的な報告(サステナビリティレポートやCSR報告書など) | 調整後排出係数(ただし、報告の目的により異なる場合もある) |
| 法定報告(温対法など) | 例として温対法では、基礎排出係数と調整後排出係数の両方での報告 |
| 取引先からの排出量報告の要求 | 要求内容や目的に応じて選択 |
基礎排出係数と調整後排出係数のどちらを選ぶべきかは、その目的や用途によって異なります。企業の自主的な報告であるサステナビリティレポートやCSR報告書で開示する際には、より実態を反映している調整後排出係数を使用するのが適切でしょう。
温対法では、都市ガスや電気、熱の使用による排出量算定において基礎排出係数と調整後排出係数の両方の数値を使用した算定結果が求められます。取引先から、排出量の報告を求められた際は、数値の使用目的を確認し、適切な排出係数を選びましょう。
中小企業が効率的にCO2排出量を算定する方法
算定に取り組み始めた企業にとって、CO2排出量を算定するには、聞き慣れない言葉や複雑なルールを理解しながら進めなければなりません。しかし、通常の業務もある中で排出量の算定に時間や手間をかけられないのが実情でしょう。CO2排出量を効率的に算定するための方法を3つ紹介します。
CO2排出量算定ツールを利用する
CO2排出量算定ツールは、電力やガスなどのエネルギー使用量を入力するだけで、自動的にCO2排出量を算定してくれるものがあります 。
ツールやプランによって内容は異なりますが、以下のような機能を備えたものがあります。
| CO2排出量算定ツールの主な機能 |
|---|
| ・データ入力の自動化 ・自動算定 ・排出源別に排出量の内訳を表示 ・CO2排出量の可視化 ・レポート作成 ・目標設定と進捗管理 ・法規制への対応 |
データ入力や計算の自動化には、手作業による人的ミスを減らせるという利点があります。また、サブスクリプション形式の料金プランを採用しているものもあり、初期費用が不要なため、導入しやすい点が魅力です。
初めてCO2排出量の算出に取り組む場合は、サポート体制も選定のポイントとして考慮しましょう。
専門家にアドバイスをもらう
CO2排出量の算定に取り組む際は、専門家にアドバイスを求めることが効果的です。算定式は複数あるため、自社の状況に適した算定方法について相談しておくことで、スムーズに算定を進められます。
地域で環境コンサルティング会社や専門家による無料相談サービスが提供されていないか、調べてみてはいかがでしょうか。
算定支援サービスを活用する
CO2排出量を効率的に算定したい場合におすすめなのが、専門知識をもつ外部企業の算定サービスの活用です。時間や手間を削減でき、信頼性の高いデータを効率的に手に入れられるメリットがあります。
算定支援サービスなら目標設計までサポートしてもらえるものがおすすめ
企業にとって、排出量算定の次の課題となるのが排出量の「削減」です。削減計画を立てるには、まず適切な削減目標が必要となります。
そこで検討したいのが、SBT認定・中小企業版SBT認定です。SBT認定とは、パリ協定の目標に基づいた科学的根拠のあるCO2削減目標を設定するための国際基準のこと。大企業も対象となる通常のSBT認定の他に、対象を限定して手続きを簡略化した中小企業版SBTもあります。
メリットがある一方「算定や海外窓口への手続きに手間がかかる」などの悩みをもつ企業も多いため、HELLO!GREENでは算定や申請の支援サービスを提供しています。
■サービスの特長
- 面倒な排出量計算を代行
- 中小企業版SBT認定の基準に沿った目標設計
- 環境省認定「脱炭素アドバイザー」がサポート
今後の展開を見据えて、効率的かつ着実に脱炭素経営を進めたい方は活用を検討してみてはいかがでしょうか。
→詳しいサービス資料をダウンロードする
基礎排出係数と調整後排出係数の違いを理解し、脱炭素経営に取り組もう
基礎排出係数と調整後排出係数は、温室効果ガス排出量算定の目的に応じて使い分ける必要があります。温対法においては、都市ガスや電気、熱の使用による排出量算定で、基礎排出係数と調整後排出係数の両方の数値を使って報告することも押さえておきたいポイントです。取引先から排出量の報告を求められた際は、用途を確認しておくと安心でしょう。
CO2排出量の算定を効率的に進めるにはツールの導入も一案です。ただし、算定の次には、排出量の削減が課題となってきます。CO2削減に向けた今後の展開も見据えて、算定を行う体制や、外部サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。